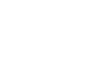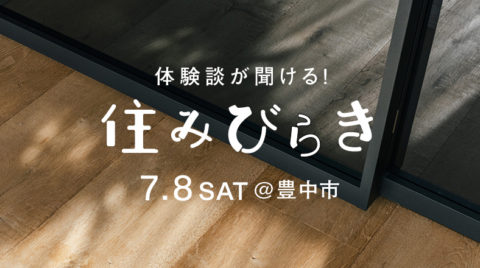古い建物が好き。古くて味がある古民家をリノベーションして暮らしたい!古民家をリノベーションしたカフェや店舗をよく見かけるようになりました。時間を経た大きな梁や、今も残る木製の建具やカワイイ昔のパーツたち。そんなものを生かした空間で暮らしてみたい!でもいざ自分で購入して、リノベーションするのって可能なの?物件はどんなふうに探せばいいの?リノベーションで気をつけることは?古民家の物件探しとリノベーションで気をつけることや進め方をまとめました。

目次
古民家の定義は?どこで探す?
「古民家」ってよく聞くけれど、明確な定義はありません。なんとなく、大きくて立派な梁が使われていて、軒先が広く、広い敷地に建っている様子がイメージされますね!よく言われる定義としては、戦前や大正時代に建てられた建物で、主に「伝統的工法」で建てられたもの。現在の木造住宅は「在来工法」という方法で建てられていますが、「伝統的工法」では、金物は使わずに仕口・継手を使って木を組んで作っていきます。強度が必要な梁には松、水を使用する台所や水回りには欅や栗を使う、など木の種類をうまく使い分けて作られているのも特徴です。
市街地ではやはり、それだけ大きな建物が残っていることがあまりないので、購入を前提として探すとなると、郊外が中心になります。大阪だと、豊能郡、泉佐野市などの南大阪エリア、八尾市や四條畷などの東大阪エリアなどでしょうか。また、泉北ニュータウンや千里ニュータウンの周辺でも開発前からの住宅があった旧村と呼ばれる地域では古民家が残っていることもあります。そのほか、奈良県や和歌山、兵庫県の北部などからご相談をいただくこともあります。
(*アフターサービス対応のため、アートアンドクラフトでは施工エリアを限定させていただいております。個別にご相談ください)
古民家物件を探す際の要注意ワード
市街化調整区域
古民家の物件探しをする際に気をつけて欲しいキーワードはいくつかあります。まずは、「市街化調整区域」。街中で不動産の取引をする場合は、ほとんどが「市街化区域」と言ってすでに市街化されていたり、今後建物を建てて土地の利用を促進していく場所に指定されています。一方で、郊外で田畑や古い建物の多く残る地域は「市街化調整区域」とされていることがあります。市街化調整区域では、建物の新築に制限があり、そのために一般的な住宅ローンを使うことが難しい場合が多いです。
農地つき
農地つきの物件にも要注意。ささやかな農地がついていて素敵!と思うかもしれませんが、農地の売買には「農地法」による制限があります。農地は原則として、”常に農業を営む”農家や農業従事者のみが購入できることと定められています。家庭菜園などで作物を作るだけでは条件はクリアできません。また、地目を変更して購入を検討する場合にも、農業委員会の許可を得る必要があり、手続きが必要です。地域によっては農地の流通の促進のために緩和規定などがある場合もありますので、個別に確認が必要です。
プロパンガス
市街地ではガスは一般的に、ガス管を通って供給されますが(都市ガス)、郊外だとプロパンガスを使用している物件もあります。プロパンガスは、契約したガス会社がガスポンベを持ってきて、ボンベからガスを供給する方法です。プロパンガスではいけないわけではありません。使い勝手に都市ガスとプロパンガスで大きな違いはありませんが、プロパンガスの方が料金が高い傾向があります。また、近くまで都市ガスが来ていれば都市ガスに切り替えることも可能ですが、道路を掘削して引き込み作業が必要なので工事費がかかることを覚悟しておきましょう。
下水管の状況
郊外の築年数が古い古民家だと、汚水と雑排水が下水管に接続されていない場合があります。敷地の近くまで下水管の設置がされていれば、接続することはできますが、ガスと同様に費用が大きくかかります。また、浄化槽を設置する場合も費用がかかります。下水がどのように処理されているかもできるだけ早い段階で確認する必要があります。

資金計画は慎重に
住宅ローンは借りられる?
築年数の古い古民家の場合、住宅ローンを借り入れるときに銀行が行う担保評価において、建物の評価はほとんど出ない場合がほとんどです。郊外の古民家で土地の面積が広い場合は、土地の担保評価で借り入れ金額が伸びる場合がありますが、物件購入と工事費の満額を借りるのは難しいことも多くあります。実際の売買金額とリノベーション費用に対していくらまで住宅ローンを使用できるかは慎重に確認が必要です。
古民家の工事費を予測するのは難しい
リノベーションを検討する際。建物の状態とリノベーションの希望内容を鑑みて、ある程度の予算を想定しながら計画は進めますが、戸建て住宅、特に古民家のような築年数が建った建物にかかる工事費を正確に想定するのは至難の業です。修繕が必要な傷みが着工してから見つかったり、ひとつひとつ建てられ方やインフラの状態が異なるため、費用の想定がつかないことが多いためです。工事費は余裕を持った金額で想定しておくこと、また、着工前の段階で予算を全て使い切った工事内容にせずに、着工後の想定外の出来事のためにある程度の余裕を見ておくことが必要です。
古民家のリノベーションのコツ
残せるものを探すところから始める。
外から見ると素敵な古民家なのに、中に入るとピカピカに工事されていて、キレイだけどなんだかなぁ、と思うことがあります。まずは、残してつかいたい建物が持つ魅力的なパーツを探してみましょう。木製の建具、今では生産されていない型ガラス、立派な木を使った梁、時間を経て色が変わりツヤツヤしている柱・・など、残したいものはたくさんあるはずです。和室から洋室にしたい場所でも、和室の要素を完全に取り除いたり隠したりする必要はありません。欄間や床の間を残したり、聚楽の壁は塗装したり・・など、アイデア次第で活かせるものもたくさんあります。新旧をうまく掛け合わせながら工事後の空間をイメージしてみてください。

断熱と耐震補強、どこまでする?
古民家を含む戸建て住宅でいつも検討事項になるのが、断熱と耐震補強。どちらも費用を惜しみなくかければ新築同等までに引き上げることは可能です。ただし、建物全体を工事対象とするとかなり大規模な工事となり立て替えた方が安かった、という結果になることも。底冷えが気になるので床下の断熱を優先する、寝室の窓にインナーサッシを取り付ける、隙間風の対策をする、など比較的簡単なことから始めるのもひとつです。どこまでの範囲をするかは予算と工事内容のバランス次第で、打ち合わせの中で決めていくのが良いでしょう。
耐震について、現在主流となっている在来工法の木造住宅は、建物をできるだけ堅固に作り自身の揺れに耐えるという考え方で作られていますが、伝統的工法では、地震の揺れに柔らかく大きく変形しながら地震力を吸収して倒壊を防ぐという考えで作られています。伝統工法で建てられている場合の耐震診断、改修については専門家の意見を聞くのがオススメです。その上で、断熱と同様にどのくらい予算をかけてどこまでの性能を目指すか、という点をよく検討する必要があります。
古民家のリノベーション事例
トイレは離れにあり、お風呂に行くには靴を履かないといけない。広いのに使えていないスペースがたくさんある。そんな理由から結婚したら建て替えるのかなぁとぼんやり考えていたというTさん。ところが奥さんは建物を一目見て、「素敵!こんな家に住みたかった!」。そこからリノベーション計画がスタート。内装は築約120年の建物の雰囲気に合わせるように選び、時間を重ねた佇まいを守りながら、今の暮らしにあった住まいへとリノベーションしました。

=======
マンションや築の浅い戸建てとはまた少し違った注意点がある古民家のリノベーション。それでも、時を経た建物でしか出せない味わいや、そこでのおおらかな暮らしはとても魅力的!古民家をリノベーションして暮らしたい、という方と一緒に住まいさがしからリノベーションまでサポートいたします。お気軽にご相談ください。
問い合わせをいただいた方には、施工事例集も無料でプレゼントしています!
大阪R不動産では、リノベーションの素材となる物件紹介もしています。
古民家物件も掲載中です! 詳しくはこちら
ー==============ー
文:松下文子 Arts &Crafts 取締役副社長